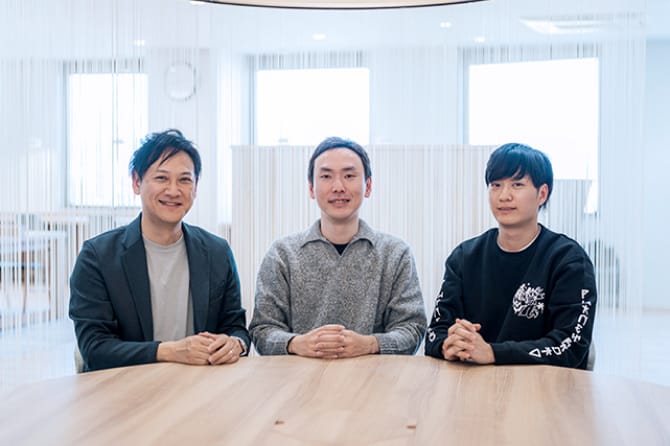【自社開発】食品スーパー向け業務システム @rms 新バージョン開発プロジェクト
事業推進力を高める、画期的な大規模開発に挑戦
個々の力を結集し、強い武器となる製品開発に成功
Member
-

K.Y
2016年入社
リテイル事業部
リテイル開発部 -

H.S
2010年入社
リテイル事業部
リテイル開発部 開発2課 -

Y.Y
2019年入社
リテイル事業部
リテイル開発部 開発1課
プロジェクトの概要について
教えてください。
-

K.Y
主力サービスのひとつ「@rms(アームズ)」は、食品スーパー向けの基幹業務システムとして、改良を重ねながら業界特有の業務課題に対応してきました。事業を拡大するにあたって、既存システムのバージョンアップが急務となり、2022年に「@rms V6 開発プロジェクト」が立ち上がりました。
-

K.Y
本プロジェクトでは、「リテイル事業をドライブする(積極的に推進し成功に導く)エンジン」をテーマに、中・大企業向けの新システム「V6」を開発。小規模企業向けに展開してきた「V3」の開発から、約20年ぶりとなる大規模開発に挑みました。開発の背景には、売上規模3,000億円以上の企業にも対応可能なシステム基盤を構築し、市場領域の拡張を目指す意図がありました。
「V6」の開発プロジェクトは、2022年4月から2024年5月にかけての2年以上にわたる長期プロジェクトとなり、さまざまな専門領域で活躍する約80名のメンバーが開発に携わりました。
開発の目玉となったのは、高速処理と大規模データの管理を可能にする新たなアーキテクチャを採用し、システムパフォーマンスの向上と高速化を実現したこと。これにより、旧バージョンの快適性を保持しつつ、100億~3,000億円規模の取引に対応し、数百におよぶ店舗間で発生する大量のデータをスムーズに処理できるようになりました。
新バージョンリリース後の評価は非常に高く、新規導入も進んでいます。
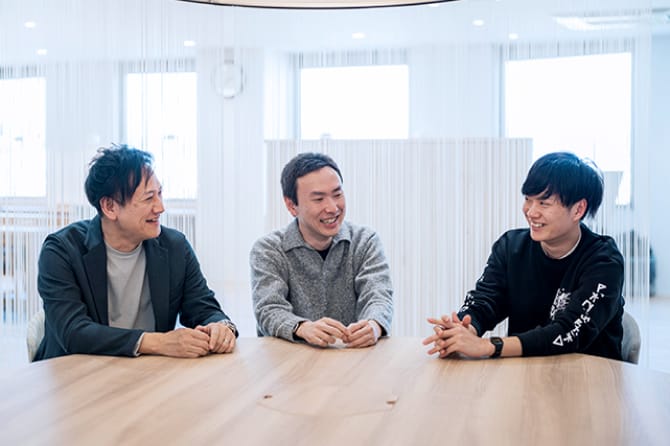
今回のプロジェクトには、
どのような役割で関わりましたか?
-

K.Y
プロジェクト責任者として「@rms V6」の開発全体を指揮しました。サービス企画を立案し、製品の方向性を定め、各チームが進むべき道筋を示しながら、リリースまで導きました。リスク管理や人材確保、リソースの割り当てなどにも力を注ぎました。
-

H.S
開発チームは、発注、売上・在庫、マスタの大きく3つに分かれていました。私は発注関連機能を開発するチームのリーダーとして、おもに進捗管理や課題管理、メンバーの管理・指導を担当。チームの方向性決定や、具体的な目標設定なども行いました。
-

Y.Y
私はマスタチームのサブリーダーとして、おもにマスタ機能関連の開発と、チーム内の技術的責任者の役割を担いました。並列処理(複数の処理を同時に実行する技術)の実装や各種ミドルウェアの内部解析など、システム全体に関わる高度な技術分野をリードし、開発を推進しました。
-

K.Y
H.Sさんは前バージョンでも発注関連チームのリーダーでしたね。H.Sさんには並列処理のロジック設計など、今回も幅広い分野で活躍してもらいました。
-

H.S
指示に従うだけでなく、下からの提案や意見を吸い上げて適宜取り入れてもらえたため、チームでやりがいを感じながら業務に取り組めました。
-

K.Y
Y.Yさんは高難度の開発に積極的に取り組んでくれましたね。今回はミドルウェアのなかにおいて旧バージョンの「統合運用管理ツール」を新バージョンに載せ替える作業も発生しましたが、詳細な内部解析はY.Yさんだからこそやり遂げられたのだと思います。
-

Y.Y
「統合運用管理ツール」の機能の一部に不便さを感じていて、それを改善したいという想いに突き動かされて、内部解析に取り組みました。
-

K.Y
重要な役割を担ってくれて、感謝しています。内部解析を引き受けてくれたおかげで、移行がスムーズになり、システムの健全性を保つことができました。

プロジェクトの進行中に多くの課題に直面したと思います。
とくにどの点に苦労しましたか?
-

K.Y
開発全体でもっとも苦労したのは高速化ですね。並列処理やさまざまな方法を試しましたが、いざやってみると期待どおりの速度が得られない。高速化において中心となって挑んでくれた2人は、それぞれの分野で壁を経験したと思います。
-

H.S
旧バージョンとまったく同じ動きを担保しながら、かつ高速化を実現する必要があったので苦労は大きかったです。
-

Y.Y
品質を追求するなかで、時間が足りないと思うこともありました。
-

H.S
私たちのチームでは、高速化のために何度もテストを繰り返し、すべての不具合を解消する作業にメンバー総出で取り組みました。高速化以外にも、各機能の完成度を最大限に高めるために、多くの時間と労力を費やしました。
-

K.Y
最後の最後まで粘り強くがんばってくれました。
-

H.S
かなりの苦労が伴いましたが、高品質のシステムを完成させることができてホッとしています。Y.Yさんが苦労したのはどんなところですか?
-

Y.Y
私は技術的な難題に直面した際に苦戦を強いられました。本番環境で作業できる時間が限られていたので、シームレスに移行し、最適化する方法を見つけ出すのに一苦労で。それと、先ほど話題に出た並列処理の設計にも苦労しました。
-

H.S
たしかに、設計段階でつまずくことはありますね。
-

Y.Y
よいアイデアが浮かべばスムーズに進みますが、行き詰まるとなかなか前に進めなくなります。そんなときは徹底的に調べて、解決策を見つけるまで考え抜くことが、壁を乗り越えるコツだと思っています。
-

K.Y
技術的な面でY.Yさんに全幅の信頼を寄せている人は多いですよ。私やH.Sさんから技術的な課題について意見を求めることもありましたね。ほかのプログラマーの悩みも解決してくれて助かりました。
-

Y.Y
みなさんに貢献できてよかったです。
-

K.Y
H.Sさんは、リーダーとして個性豊かな技術者たちを束ねることに長けているので、マネジメント面でも期待どおりに力を発揮してくれたなと感じています。
-

H.S
ありがとうございます。K.Yさんはマネジメントで苦労したことはありましたか?
-

K.Y
「@rms」の開発には、「GeneXus(ジェネクサス)」という開発ツールを使用していますよね。社内でも使いこなせるメンバーは限られているので、人材の確保に苦労しました。外部技術者の協力が必要だったため、適切なパートナーさん探しに奔走しましたよ。
-

H.S
開発はテレワーク中心だったので、全体を管理するのはたいへんだったと思いますが、全国各地から優秀なメンバーを集められたことは幸いでしたね。
-

K.Y
80人規模の大規模プロジェクトをほぼリモートで進行したことは、私にとっても貴重な体験でした。対面の会議を交えつつ、リモート主体のハイブリッドな運用体制を構築した経験は、今後のプロジェクトに大いに活かせると思います。

プロジェクトを通じて感じた魅力、プロジェクトに関わった意義について教えてください。
-

K.Y
高速化への取り組みがめざましい結果を生んだことに、驚きと喜びを感じました。とくに発注締め処理や商品マスタ取込などの注目機能の速度が大幅に向上し、製品の利便性が格段に増した点は強調すべきことでしょう。お客様のビジネスへの貢献度も高まったと思います。
-

H.S
私たちのチームが手がけた発注締め処理機能の速度改善は、誇れる成果だと思っています。速度目標を達成した瞬間は、今でも忘れられません。お客様に提供した際もほぼトラブルは発生せず、チーム全員で「やりきった」という達成感を味わいました。協力会社さん含めチーム一丸となって取り組み、想いを共有できたことは、リーダーとしてとても嬉しかったです。
-

K.Y
私にとっても嬉しい成果でしたよ。中・大企業に向けて胸を張って提供できる製品が完成して、このうえない達成の喜びを味わいました。
Y.Yさんは、どんな魅力を感じましたか? -

Y.Y
私にとって魅力的だったのは、未知の技術領域に挑戦する機会を得られたことです。たとえば並列化について、構想はあったものの具体的な実装方法は十分に理解できていなかったので、挑戦の場をもらえてモチベーションが高まりました。関連する技術や手法をじっくり調べるなかで構想がクリアになり、最終的に実現することができていい経験となりました。
-

K.Y
地道に取り組んだことが成果として表れやすいのが、この仕事のやりがいかもしれませんね。探究心のある人は、どんどん成長していけると思います。
ではプロジェクトに参加した意義を、どう捉えていますか? -

Y.Y
挑戦を後押ししてくれる社風が、技術者としての成長を支えているのだと改めて実感しました。私にとって未知の領域に取り組むことは、キャリアを深める大きな原動力となっています。プロジェクトに参加した意義は、それに気づけたことだと思っています。
-

K.Y
なるほど。H.Sさんはいかがですか?
-

H.S
大きなチームを率いて目標達成できたことは、とても有意義な経験でした。前バージョンでリーダーを務めたときは5名程度のチームだったので、それほど苦労しませんでしたが、今回は関与する人数が増えて最初は束ねるのに苦労しました。
-

K.Y
今回はそれだけ大きな開発だったということですよね。対処すべき課題も多かったと思います。
-

H.S
それが、プロジェクトの後半になるにつれチームの団結力が増し、みんなでひとつの製品を作り上げる一体感とたのしさを実感できるようになったんです。私にとって、チームで業務に取り組むことが、働く意欲を高めるのだと自覚しました。
-

K.Y
2人とも、プロジェクトへの参加に意義を見出していたようで安心しました。私自身は、事業を推進するための強力な武器となる高性能なソフトウェアが完成したことは、当社にとって非常に意義深いことだと感じています。実際に、製品が市場で売れ始めていることが成果の証です。「V6」が当社の成長を加速させることを期待したいと思います。

プロジェクトが終了した今、
どのような成果を感じていますか?
-

K.Y
「リテイル事業をドライブする」ことを目標にして開発に挑んできましたが、力強い製品が無事完成し、大きな達成感と成功体験を得ることができました。この製品を通じて、今後の事業拡大が十分に見込めると思います。H.Sさんは、成果についてどう感じていますか。
-

H.S
私は、プロジェクトを通じて各メンバーが成長し、次世代のリーダー候補が育ってきたことも成果だと感じます。それぞれの考え方が変化し、以前よりも広い視野をもって仕事に取り組めるようになりました。「V6」の開発中も、自分の担当領域だけでなく全体を見て開発に取り組んだからこそ、不具合(バグ)を潰しきることができたと思います。
-

K.Y
関わったメンバーは頼もしく成長していますね。Y.Yさんはどんな成果を感じていますか。
-

Y.Y
自分にとっての最大の成果は、技術力が大きく向上したことです。プロジェクトを通じて、品質を追求するための知識が増え、スケジュールの管理能力も向上し、多方面でスキルアップできました。またチーム全体としてのノウハウや知見が蓄積され、次のプロジェクトへの貴重な財産となったと思います。
-

K.Y
新たなソフトウェアを開発する舞台が整ったことも、成果のひとつですね。当社は未知の世界にどんどんチャレンジしていける社風なので、今後も新しい技術を使いながら、市場で求められているソフトウェアの開発に積極的に取り組んでいってほしいと思います。